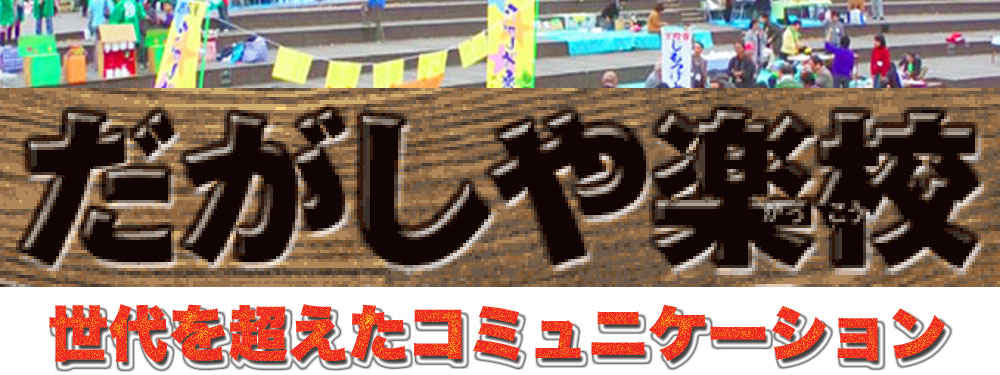だがしや楽校とは
“だがしや楽校”とは、学校では学べないもうひとつの学びの場で、誰もが「手軽に」お祭りの屋台のような形で、自分の「趣味・特技・遊び・学び・作品」などを「みせ(店・見せ)る集いです。
2008年12月20日までに作成した“だがしや楽校”の紹介文
私たち大人でも(誰にでも)、ちょっとした「趣味・特技・遊び・学び・作品」を持っています。それは、些細なことでも、ちょっとしたことでも、くだらないと思うようなことでも、良いんです。それが“駄菓子屋”の“駄”です。私たち大人は、このような“駄”を見下し、意識もしませんでした。しかし、これでは、子どもたちの世界に入り込むことはできません。私たち大人は、大人のプライドによって、子どもたちの世界を見下していなかったでしょうか。しかし、それは、人として大事なことを見失っているのです。
“だがしや楽校”の考え方は、私たち大人が子どもの目線に立つことです。そのためには、車移動の速さでは見つけることができません。歩くことで見えてくるのです。
このような視点で自分を見つめ直すと、今まで気付かなかった自分の「趣味・特技・遊び・学び・作品」が見えてきます。それを“だがしや楽校”で「見せ・店」るのです。“だがしや楽校”は私たち大人にとっては「自分見せ・店」の場なのです。
子どもたちの目線で自分を見せると、子どもたちが集まります。そこで初めて、子どもたちと大人たちとの(世代間)コミュニケーションが成り立ちます。そこでは、子どもたちも大人から学びますし、大人は子どもたちから学びます。また、子ども同士、大人同士でも、交流しながら、学び合います。
子どもたちが“だがしや楽校”で学ぶのは、
たくさんの人と集うことの楽しさ(関わりの量)、集団遊びや異年齢の子どもとの交流を通して人づきあいの経験を重ねること(関わりの質)、遊びを作り発展させていくなかで創意工夫していくこと(関わりの深さ)、さらには、人づきあいのマナー、物事の善し悪し、小銭のやり取りで計算の仕方・経済の仕組みについての学び、親や先生とは違う存在の大人との関わり→子ども社会のカウンセラー。この部分は東北芸術工科大学・片桐隆嗣教授の説明分を一部引用
一方、大人は子どもたちから、今の子どもたちが、どんなことを思っているのか、どんなことに関心があるのか(“だがしや楽校”では、子どもたちは意外な関心の示し方をする)を体験学習することで、子どもたちへの育み方を学ぶ場なのです。
また、大人にとっては、自分の生き方も学ぶ場であり、自分が住んでいる地域(地域社会)を学ぶ場でもあります。
このように“だがしや楽校”は「自分見せ・店」の集いですので、“だがしや楽校”には「こうしなければならない」というようなルールはありません。すなわち、人それぞれの“自分のだがしや楽校”があるのです。あなたにはあなたの、私には私の“だがしや楽校”があるのです。
だから、小さな公園で、2~3人の大人が、僅か数人の子どもたちといっしょに集うのも“だがしや楽校”です。一方で、1日に何万人も集うのも“だがしや楽校”なのです。地域づくりのために“だがしや楽校”を活用することもあります。例えば、中心商店街イベントといっしょに開く“だがしや楽校”が、それです。高齢者の生き甲斐づくりのための“だがしや楽校”もあります。
つまり、“だがしや楽校”では、必ずしも子どもたちを意識する必要はありません。大人同士の“だがしや楽校”もありです。
このように何でもありの“だがしや楽校”ですので、“だがしや楽校”ではお互い(のやり方)を認め合う心を育むことができます。
まずは、大人のプライドを捨て、狭い視野から脱却し、“だがしや楽校”を通して、私たちが気付かなかった世界、見過ごしてきた世界に入り込みましょう。それが、新たな地域づくり・まちづくり・人づくりの始まりになるのです。
2005年に作成した説明文
続いて、2005年に作成した説明文をご紹介します。山口の“だがしや楽校”に対する思いの違いをお楽しみください。
例えば私の場合、子どもの頃、家の近くに駄菓子屋がありました。その店は、小学校へ通う道の交差点の角にありましたので“かどみせ”と言ったものでした。“かどみせ”には駄菓子がいっぱい並んでいましたが、私が特に買ったのは、アイスキャンデー(誤字ではありません)でした。アイスキャンデーは、ミルクとあずきの2種類ありました。木の棒(スティック)にさされたアイスキャンデーは、今のアイスクリームと違ってかたいものでしたが、それでも美味しく食べたものでした。その“かどみせ”には、おばちゃんがいました。そのおばちゃんは「元気に遊べよ」とか「アイスキャンデー食い過ぎて、腹いだくすんなよ」などと言ってくれました。
“だがしや楽校”のコンセプトはここにあります。「お店のおばあちゃん」とのやりとりを通じて、社会のルールやコミュニケーション能力を自然に身に付けることができた「近所の駄菓子屋」の教育効果に注目した山形県上山市の中学校教諭、松田道雄さんが仕掛け人となって始まった活動が“だがしや楽校”なのです。
“だがしや楽校”は、人と人とのコミュニケーションを学ぶ場と言っても良いでしょう。「すべてのアイディアの玉手箱は駄菓子屋です」というコンセプトから“だがしや楽校”と名付けました。
“だがしや楽校”は、例えば“昔の遊び教室”と似ているかもしれません。しかし、決定的に違うのは、“だがしや楽校”はお祭りみたいな雰囲気になるのです。屋台が公園にたくさん並んでいて・・・子供の元気な声が聞こえてきて・・・、そんな雰囲気なのです。
そして、誰もが先生になれるのです。教える人は専門家でなくて良いのです。子どもたちに自分の得意なことを自由な形で伝えたい、それだけであなたも先生になれるのです。あの“かどみせ”のおばちゃんは、専門家でもなんでもなかったのです。
“だがしや楽校”は、単に大人が子供に教える場ではありません。子供同士、大人同士、そして大人が子どもたちから学ぶ場でもあります、世代を越えたコミュニケーション、それが“だがしや楽校”です。
あなたも“だがしや楽校”を開いてみませんか。
また、“だがしや楽校”に相応しい遊び心たっぷりの笑品(商品)もご紹介ください。笑品(商品)とは、例えば、米沢市の“おっぱいプリン”です。
さらに、“だがしや”と呼べるお店があればご紹介願います。
そんな“だがしや楽校”のCD「だがしや楽校のススメ」がテイチクより発売されています。CDには、ゆき彦さんと丹波恵子さん(お二人とも山形県内在住のシンガーソングライター)の歌を中心に、松田さんをはじめ“だがしや楽校”に関わりのある人たちの楽しいトークも収録されています。
CDの詳しいことは“だがしや楽校”のホームページをご覧いただきたいと思いますが、“だがしや楽校”に興味を持たれましたら、ぜひ1枚、お買い求めいただきたいと思います。なお、このCDのブックレットについては、私(山口)も若干ながらお手伝いさせていただきました。